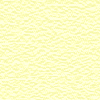英 名 : Sumac
学 名 : Rhus javanica
別 名 : フシノキ(五倍子の木)
別 名 : カチノキ(勝の木)
科 名 : ウルシ科
属 名 : ウルシ属
種 類 : 落葉小高木
花 期 : 晩夏〜初秋
原産地 : 東南アジア〜東アジア
撮影場所:名古屋市千種区・東山植物園
雌雄異株です。
幹は灰褐色で、赤褐色で楕円形の皮目があります。
葉は長さ30〜60㎝の奇数羽状複葉で互生します。小葉は7〜13枚で長さ5〜10㎝、幅3〜6cmの長楕円形で、脈が窪み、縁には粗い鋸歯があり、先が尖ります。
ウルシ科の他種と違って、複葉の中軸に翼があるのが特徴です。
秋早くに綺麗に紅葉して目を引きます。
枝先の長さ30cmほどの円錐花序に黄白色の小さな花を咲かせ、泡を吹いたような感じになります。
雌花には長さ2mmほどの5枚の花弁があり、中心に3つに分かれた柱頭をもつ雌しべがあります。
雄花は反り返る5枚の花弁をもち、5本の雄しべが突き出ます。
葉に「ヌルデノオオミミフシアブラムシ」が寄生すると「ヌルデノミミフシ」と呼ばれる虫こぶができます。
虫こぶは「五倍子(ごばいし)」あるいは「付子(ふし)」と呼ばれ、タンニン(tannin)を多く含むため、昔はお歯黒や白髪染めの原料として利用されました。
ウルシ科ですが、ヤマウルシ(Rhus trichocarpa)やヤマハゼ(Rhus sylvestris)ほどは被れません。虫こぶを触ると被れる場合もあるようです。
果実は直径3mmほどの扁球形の核果で、多数垂れ下がり、黄褐色に熟します。外果皮には茶褐色の細毛が密生します。
果実は白色の物質(リンゴ酸カルシウム)を分泌して被われ、台湾や日本の山間部ではこれを塩の代用にしました。
果実はワックスを含んでおり、ロウが採集できます。ウルシ科の実から採取したロウは数日間天日に晒すと白蝋になり、和蝋燭の原料になります。
和名は、幹を傷つけて白い汁を採り塗料として使ったことから「塗る手」に由来します。
材は色が白く材質が柔らかいことから、木彫の材料、木札、木箱などに利用されます。
秋に果実を日干しにして乾燥させたものを生薬で塩麩子(えんふし)といい咳止めや下痢止めに薬効があります。
葉を乾燥させたものは生薬で塩麩葉(えんふよう)といいます。
別名のフシノキは生薬の麩子(ふし)がとれる木という意味です。
別名のカチノキは、聖徳太子が蘇我馬子と物部守屋の戦いに際し、本種で仏像を作り馬子の戦勝を祈願したとの伝承に由来します。
属名の「Rhus」は、ギリシャの古名「Rhous」をラテン語化したものです。
種小名の「javanica」は、インドネシアのジャワ島を意味します。

撮影場所:名古屋市千種区・東山植物園

撮影場所:名古屋市千種区・東山植物園